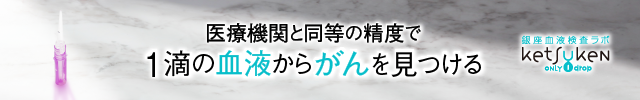がんの進行度合いは?
さて、がんの告知を受けて慌てて情報収集を始めます。
まずは手っ取り早くネット検索といわゆる家庭医学の前立腺がん解説書を購入して読んでみました。
医学の進歩も日進月歩だろうから書籍はその時点で発行年月日が比較的新しい本を選びました。
こちらの本ですが、前立腺がんに関する全般的な内容が分かりやすくまとめられており、最初に手に取る本としておすすめします。
ネットでは国立がん研究センターのがん情報サービスというサイトに一通りの情報がでており、がんの進行度合いを示す指標としてTNM分類というのがあると書いてあります。
前立腺がんの病気分類
|
T1 |
直腸診で明らかにならず、偶然に発見されたがん |
|
T1a |
前立腺肥大症などの手術で切り取った組織の5%以下に発見されたがん |
|
T1b |
前立腺肥大症などの手術で切り取った組織の5%を超えて発見されたがん |
|
T1c |
PSAの上昇などのため、針生検によって発見されたがん |
|
T2 |
直腸診で異常がみられ、前立腺内にとどまるがん |
|
T2a |
左右どちらかの1/2までにとどまるがん |
|
T2b |
左右どちらかだけ1/2を超えるがん |
|
T2c |
左右の両方に及ぶがん |
|
T3 |
前立腺をおおう膜(被膜)を越えて広がったがん |
|
T3a |
被膜の外に広がっているがん(片方または左右両方、顕微鏡的な膀胱への浸潤) |
|
T3b |
精のうまで及んだがん |
|
T4 |
前立腺に隣接する組織(膀胱、直腸、骨盤壁など)に及んだがん |
|
N0 |
所属リンパ節への転移はない |
|
N1 |
所属リンパ節への転移がある |
|
M0 |
遠隔転移はない |
|
M1 |
遠隔転移がある |
TNM分類の例
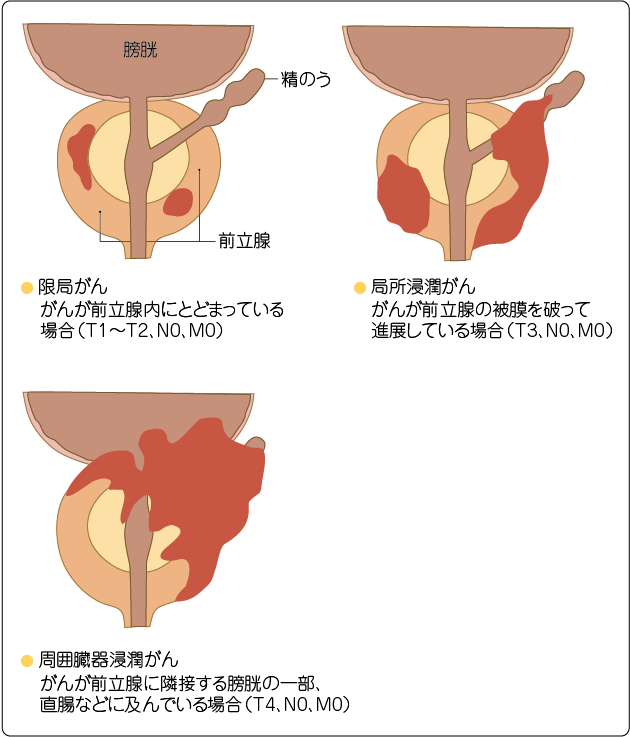
でも病院でもらった資料にはTNM分類の話は書いていなくて、進行度合いがABCで書かれていました。書籍の方で確認するとABCD分類という方法もあり、病院のプリントはこちらで書いてあることが分かりました。
医師の説明ではB~Cのどこかだろうという説明だったと思います。
ABCD分類(ジュエット分類)
A1 :前立腺内にとどまっている高分化がん
A2 :前立腺内に広がったがんか低分化がん
B1 :前立腺の片葉に病変がとどまっている単発のがん
B2 :前立腺の片葉全体か両側にまたがっているがん
C1 :前立腺の被膜や被膜外に広がっているがん
C2 :膀胱頸部か尿管の閉塞が見られる
D1 :骨盤内のリンパ節にがんの転移が見られる
D2 :D1より広い範囲のリンパ節や骨、肺、肝臓などの遠隔部位にがんの転移が見られる
出展:赤倉功一郎『前立腺がん』主婦の友社〈よくわかる最新医学〉2019年
転移の有無はこれから検査 CT検査・骨シンチ
これから転移の有無を調べるためにCT検査と骨シンチグラフィーという画像診断を受けるということでした。CT検査は今までも人間ドックなどで受けたことがあり何となくわかりますが、骨シンチグラフィーは初耳です。
前立腺がんは骨に転移しやすいということで、骨シンチグラフィーは骨への転移の有無を調べる検査だというこが分かりました。
弱い放射線を発する物質(アイソトープ)を注射し、全身に行き渡ったころに特殊なカメラで撮影をすると、注射した物質が骨の異常部位に集まる性質があるため、転移の有無が診断できるとういうことのようです。
詳しい説明は専門サイトなどに譲りますが、CTでリンパ節や肺などの臓器への転移、骨シンチグラフィーで骨への転移を調べるということのようです。
グリソンスコア?
それから私の場合、グリソンスコアという数値が8で、これは悪性度の高い分類になると説明は受けたものの何のことかよくわかりません。
これも調べてみると生検で採った細胞の組織構造と増殖パターンを顕微鏡で調べ、1~5のパターンのうち、最も広がりの大きいパターンと次に大きいパターンのスコアを合計した数値ということです。
同じグリソンスコア7でも(4+3)と(3+4)の2ケースがあり、この場合前者の方が悪性度が高いということでした。
私の場合は8なので、(4+4)、(5+3)、(3+5)の3パターンがあるのでしょうか。調べてみてもグリソンスコア7の例は解説されていますが、6や8のことは書かれていません。グリソンスコア6は悪性度が低いと分類されていますが、(5+1)のような組み合わせはないんでしょうか?
X病院の診察はかなり立て込んでいて、医師も説明にあまり時間をかけられないのかも知れませんが、かなりあっさりした説明でした。医師の説明と数ページのプリントで治療法を選択というのはちょっと無理だと思いました。
がん拠点病院
病院については「がん診療連携拠点病院」(以下、「がん拠点病院」という)というのがあり、私の通っている病院も「がん拠点病院」だということが分かりました。ていうか、最初にちゃんと調べとけってことですね(汗)
「がん診療連携拠点病院」とは(出展:国立がん研究センター がん情報サービス)
専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の整備、患者・住民への相談支援や情報提供などの役割を担う病院として、国が定める指定要件を踏まえて都道府県知事が推薦したものについて、厚生労働大臣が適当と認め、指定した病院です。
また、「がん相談支援センター」というのも設置されているということで、困ったときの相談もできるのかと心強く思いました。(後に失望に変わりますが)
「がん相談支援センター」とは(出展:国立がん研究センター がん情報サービス)
全国のがん診療連携拠点病院などに設置されている「がんの相談窓口」です。患者さんや家族あるいは地域の方々に、がんに関する情報を提供したり、相談にお応えしています。がん専門相談員としての研修を受けたスタッフが、信頼できる情報に基づいて、がんの治療や療養生活全般の質問や相談をお受けしています。
さて、これから悩ましい治療法選択の検討が始まります。
※本ブログは医学の専門家ではない一患者の治療記録です。可能な限り正確な情報を記載するよう努めていますが、必ずしも正確性や安全性を保証するものではありません。当サイトをご利用することで発生したトラブルに関しては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。